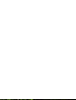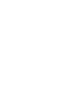地籍調査について
更新日:2025年05月23日
地籍調査とは
地籍調査とは、土地の戸籍調査ともいうべきもので、一筆ごとの土地について、位置・形・地目・面積などを明らかにするために法務局に備え付けられている公図をもとに、公図を修正しながら行われる調査です。
現在利用されている公図などは明治初期の地租改正の時に作成されたものです。そのため、当時の測量技術の未熟さやその後の土地の異動などで、実際には現況との食い違いが随所に見られ、その役割を十分に果たしていないのが実情です。また、面積についても登記簿と実測面積とに差が見られる等、正確さを欠いています。このため、市が主体となって、国土調査法に基づき全国的に統一された基準により一筆ごとの土地について現地調査と最新の技術による測量を行い、地籍図(精度の高い地図)と地籍簿(面積や地目を記入したもの)を作成し、土地所有者の閲覧を経て県知事の認証を受けた後、法務局に送付します。
法務局に送付された地籍簿に基づき土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

杵築市の地籍調査の概要
|
1. 総面積 |
2. 要調査面積 | 3. 調査完了面積 | 4. 進捗率(3./2.) | |
| 杵築市全域 | 280.08 ㎢ | 272.61 ㎢ | 189.13 ㎢ | 69.38 % |
| (旧杵築市) | 90.30 ㎢ | 88.97 ㎢ | 55.76 ㎢ | 62.67 % |
| (旧山香町) | 143.71 ㎢ | 137.57 ㎢ | 87.30㎢ | 63.46 % |
| (旧大田村) | 46.07 ㎢ | 46.07 ㎢ | 46.07 ㎢ | 100.00 % |
(注)上記表にはR6年度調査分まで含んでいます。(令和7年4月1日現在)
地籍調査実施字一覧表(市全域)
R7地籍調査事業年度別実施字一覧表(市全域) (PDFファイル: 193.0KB)
(注)上記一覧表は、令和7年度一筆地調査実施中の字まで含んでいます。
地籍調査の事業費
国・県・市の補助金により事業を実施しますので、個人の方が費用を負担することはありません。 ただし、この事業において所有権移転登記(名義変更)はできません。
令和7年度調査実施地区(一筆地調査地区)
【杵築地域】
[大内地区]
調査地区・・・大字大内の一部(字 立岩、浜、塩浜)
調査面積・・・0. 52㎢ [ただし、土地改良事業・圃場整備等は除く]
[横城地区]
調査地区・・・大字横城の一部(字 高岩、大福田、長谷、富山、山ノ田、福手場、尾払口、平河原)
調査面積・・・1.02㎢ [ただし、土地改良事業・圃場整備等は除く]
【山香地域】
[上地区]
調査地区・・・大字南畑の一部(字 皇后石、熊ヶ倉)
調査面積・・・1. 06㎢ [ただし、土地改良事業・圃場整備等は除く]
地籍調査の進め方
地籍調査の進め方や実施時期は下表のファイルを参考にしてください。
地籍調査の主な作業順序 (PDFファイル: 139.0KB)

一筆地調査(現地調査)について
一筆地調査(現地調査)とは
法務局の土地登記簿と字図をもとに作成した調査図を、土地所有者(関係者)立会いのうえで現地と照らし合わせ、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界を調査確認することです。また、一筆地調査は地籍簿及び地籍図作成の基礎であり、重要な調査となります。地籍調査の作業工程中、最も重要な工程です。現地調査立会者は、現地調査日までに隣接の土地所有者と境界を確認し、調査が円滑に進むようご協力をお願いします。

調査の要点
1.登記簿に登記されている表示に関する事項と現況は適正か。
2.登記もれの土地がないか。
3.公図の表示(地番、形状、配列等)は現地と一致するか。
4.筆界(境界)は、どこか。
筆界の確認調査は、所有者がその土地の筆界に関する記録や慣習等を参考にして、隣接地の所有者(利害関係を有する者等)の確認を得たうえ設置した筆界杭により確認します。
地籍調査の必要性
現在、登記所備えつけの土地台帳や字図の多くは、明治初期の地租改正によって作られたもので、当時の測量に対する考え方や測量技術が現在のように精密でなかったこと、また、長い年月が経っているため面積や形状等が現地と必ずしも一致していません。
以上のことから、皆様の土地を最新の測量技術と調査によって明確にし、その権利を保護できるものにする必要があります。

一筆地調査(現地調査)では、次の調査を行います。
(1)所有者の調査
登記名義人と現地とが一致するか否かの調査。
<注意事項> 相続・売買・交換等で登記名義人と土地使用者が異っていた場合、地籍調査事業においては、名義変更の処理はできませんので、個人で手続きをしていただくことになります。
(2)分割の調査
一筆の土地に異なる地目があった場合、分割できます。
(3)合併の調査
所有者及び地目が同じ、かつ字を同じくして接続している土地などが二筆以上ある場合、一筆に合併することができます。
(注)ただし、下記禁止事項に該当する土地に関しては、合併できません。
「合併禁止事項」
☆いずれかの土地に所有権以外の権利に関する登記 (抵当権、地上権、要役地地役権等)がある場合。
(注)ただし、先取特権、質権又は抵当権に関する登記で登記原因、その日付、登記目的及び受付番号が同一である場合、 合筆があったものとして調査することができます。
☆いずれかの土地に所有権の登記がない場合。
☆共有地について持分が異なる場合。
(4)地目の調査
一筆毎の土地の現況及び土地全体としての利用状況を確認し、地目を判定します。
(5)筆界の調査
筆界とは、登記されている一筆の土地の範囲を示す線(境界線)のことです。登記簿に登記されている現在の土地の筆界を前提として、字図を修正します。
「現地確認不能」について
現地確認不能とは、登記された土地でありながら、現地において確認することができない土地。
(1)既登記の一筆の土地が長狭物(道路、用悪水路、河川などの敷地)となっている場合。
(2)滅失地・不存在地でありながら所有者の承認が得られない場合。
滅失地とは・・・土地の一部又は全部が陥没して、海又は湖の一部になる等物理的に消滅した土地。
不存在地とは・・・二重登記や登記簿はあるが公図に表示がないなど当初から存在しない土地。
※「筆界未定」について
一筆地調査(現地調査)の際に、隣接する土地との境界が紛争等で決まらなかったり、雑草木等が伐採されておらず、現地で筆界を確定できない土地は「筆界未定」となり、確認できなかった隣地との境界線は地図には表示されません。登記所送付までに当事者間において境界が確定しない場合は、当該地の調査・測量ができないので、国土調査の成果はあくまで「筆界未定」となり、その後に境界が決まっても地籍調査で処理することはできませんので、土地所有者本人の責任において処理すべきことになります。
※「筆界未定」となった場合(登記所等の主な取り扱い)
1. 筆界未定地を解消する場合、測量や登記といった諸費用は、すべて当事者の負担となります。
2. 土地の一部を売買する場合や抵当権等を設定することが難しくなります。
3. 地目変更、分筆、合筆、地積更正の登記申請については、「筆界未定」を解消してからでないと基本的には受理されません。
土地所有者等は何をすればよいか
1. 調査を円滑に進めるうえで、現地調査日(立会日)までに、隣接の土地所有者と事前に立会い、境界を確認しておいてください。
2. 隣接地との境界線が雑草木で密集している場合は、境界線を中心に1メートルほど伐採して見通しをよくし、杭打ちや測量が出来るようにしておいてください。
3. 現地調査の立会日程表をよく確認し、必ず立会いに来ていただけますようご協力をお願いします。なお、所有者が出られない場合は、代理人でもよいです。
(注)ただし、代理人の場合は、委任状が必要になります。
4. 売買や譲渡などで権利移転の登記が済んでいない土地及び抵当権を抹消できる土地がある場合は、法務局にて早めに手続きしましょう。
測量作業に伴う土地所有者等へのご協力について
1. 測量作業等の実施に伴い、測量業者が現地に測量杭を打ちますので、抜いたり動かしたりしないようにお願いします。
(現地調査で確認した一筆ごとの土地について、面積を正しく測量するために必要な杭です。)
2. 測量作業に伴い立竹木等(障害物)により測量に支障がある場合は、測量業者が伐採をすることがありますのでご了解願います。
3. 杭の区別について、測量業者が打つ杭は上部が「赤色」、境界杭は、「黄色」または「白色」です。(プラスチック杭)


関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 地籍調査係
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-